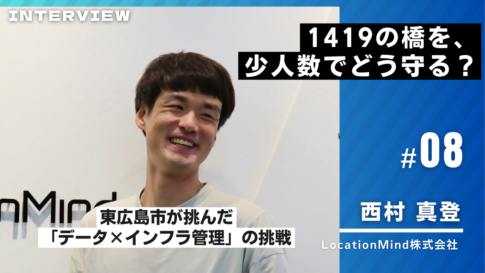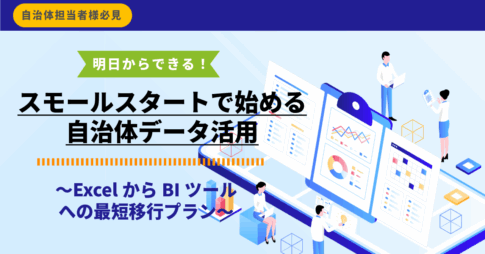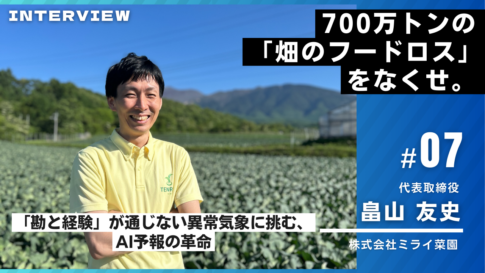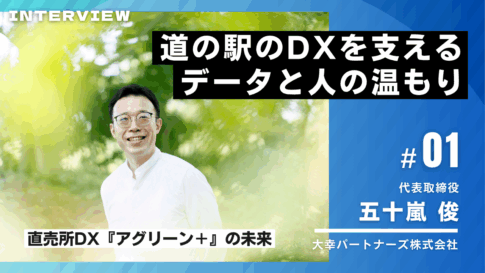業務は増える一方なのに人も予算も増えない、そんな現実に悩む担当者は少なくありません。住民への説明責任も年々厳しくなり、「なぜその政策なのか」を客観的に示すことが求められています。
この状況を打開するカギが、データに基づく意思決定で「効果の高い政策だけに集中投資」できるEBPMです。本記事では、EBPMの基本概念から実践的な導入手順、神戸市・八女市の成功事例まで詳しくお話します。
EBPMとは?基本概念をおさらい
EBPMを活用するには、「理論」と「実務」をつなぐための知識を身につける必要があります。ここでは、EBPMの定義から特徴、従来手法との違いを見ていきましょう。
EBPM(Evidence-Based Policy Making)の定義
EBPM(Evidence-Based Policy Making)とは、データや証拠(エビデンス)に基づいて政策を作り、見直す手法です。日本語では「根拠に基づく政策づくり」と呼ばれています。
EBPMでは、従来のように担当者の経験・勘だけで判断するのではなく、統計データや調査結果、過去の事例分析などの客観的な根拠を集めて政策を組み立てます。政策を実行した後も、同じようにデータを使って効果を測定し、うまくいかなかった部分を改善していくのが特徴です。
このデータ重視のアプローチにより、政策の成功確率が高まり、限られた予算をより効果的に使えるようになります。また、政策決定の過程が透明になるため、住民への説明責任も果たしやすくなります。
従来の政策立案との違い
従来の政策立案は、担当者の経験や個別事例に頼りがちな「エピソードベース」の性質を持っていました。これに対して、EBPMは話し合いの出発点をデータに置くことで、議論を筋道立てて進めることを可能にします。
評価においても大きな違いが見られます。従来は判断基準が曖昧になりがちという課題がありましたが、EBPMでは数値や内容面の指標で効果をはっきりと測定する手法となっています。さらに、PDCAの循環により、質を継続的に向上させていく特徴があります。
地方創生の分野では、この手法により人口減少対策や地域経済活性化、移住・定住促進の取り組みを冷静に見比べることが可能になります。
なぜ自治体はEBPMに取り組むべきなのか?
人口減少と財政制約、そしてデジタル化の進展により、EBPMに取り組む自治体が増えています。以下、その背景となる環境変化と住民生活への波及について解説します。
限られた予算と人員を有効活用する必要がある
人口が減ると税収も減ります。一方で、高齢化により医療・介護にかかる費用は増え続けます。つまり、使えるお金は減るのに、必要な支出は増えるという状況が生まれているわけです。
このために自治体は、限られた予算と職員で住民サービスの質を保たなければなりません。どの事業に予算を投じれば効果が上がるかを常に確認し、優先順位を見直すことが重要です。
デジタル化でデータが使いやすくなった
近年、政府主導のDX推進により、住民票、税、社会保障といった行政情報がデジタルデータとして整備・標準化されつつあり、EBPMに活用できる環境が整ってきました。これまでバラバラに保管されていた情報をまとめて分析することで、今まで気づかなかった地域の問題や住民のニーズが見えてくるようになります。
住民への説明責任がある
なぜその政策を行うのか、どれくらいの効果があったのかをデータで示すことは、行政における当然の責任です。根拠をともなう説明機会が増えるほど、住民の納得感が高まり、結果として協力が得やすくなります。
自治体におけるEBPM導入のメリット
財政課には予算配分の根拠が、現場には改善のヒントが、経営層には説明責任を果たすための判断材料が得られます。ここでは、住民の生活に直結する成果を念頭に、EBPM導入による3つのメリットを解説します。
政策効果を客観的に評価できる
従来の「効果があったと思う」といった感覚的な判断とは異なり、EBPMでは、データで政策効果を検証します。たとえば、子育て支援事業なら「出生率が何%上昇したか」「転出する子育て世帯が何世帯減少したか」といった具体的な指標で成果を測定します。
こうして得られた結果から成功要因や改善点が明確になり、翌年度の施策に的確に反映できるのは、大きなメリットです。議会・住民への報告においても、根拠が付随する説得力のある説明ができるようになります。
限られた予算を効果的に配分できる
自治体の予算は限られています。EBPMによって各事業の効果を可視化すれば、優先度の高い施策に、的確に予算を配分できるでしょう。たとえば、効果の薄い事業は縮小し、効果の高い事業には重点的に投資することで、無駄を減らし、住民サービスの質向上につなげられます。
職員のスキル向上と組織文化の変化
EBPMの実践は、職員がデータを読み解く力や統計的な分析力を身につける機会になります。「経験と勘」に頼る判断から「データに基づく判断」への移行が進むことで、組織全体に新しい文化が根づくでしょう。また、研修制度や人事評価と組み合わせれば、こうしたスキルを継続的に伸ばし、現場でのデータ活用を定着させられます。
自治体のEBPM成功事例
ここでは、神戸市と八女市におけるEBPMの導入事例をご紹介します。データ担当やDX推進の立場から見た、現場の「困りごと起点」の取り組みを見ていきましょう。
神戸市:庁内データの一元化と現場での活用を支える仕組み作り
神戸市では「神戸データラウンジ」という仕組みを作り、市役所内のバラバラに保管されていたデータを一ヶ所に集めて見やすくしました。専門知識がない職員でも簡単に使えるよう工夫されており、現場からの分析・提案を後押ししています。
さらに庁内のデータを集約し、グラフ・表で見やすく表示する基盤を整えたことで、資料作成のスピードと提案の質を向上させました。これまで各部署がバラバラの数字を見て話し合っていたのが、職員全員で同じ数字を見ながら議論できるようになったのは大きいでしょう。
「神戸データラウンジ」導入後は、部署間での各種調整にかかる手間が大幅に減ったといいます。実際、新型コロナウイルス感染症対策などの緊急時でも、「見える化」された指標が迅速な判断と住民への情報提供を支えました。
【出典】神戸市「行政データの利活用に関する有識者会議~R5年度の取組状況等報告~」 URL:https://www.city.kobe.lg.jp/documents/60389/07_shiryou.pdf
福岡県八女市:専用ツールで住民ニーズを詳しく把握
八女市では、BI(ビジネスインテリジェンス)ツールという専用のソフトを使って、人口の変化や住民の生活実態を「見える化」しました。
BIツールとは、大量のデータを分析して結果をわかりやすく表示してくれるツールのことです。データに基づいて対策を考え、実施後の効果を確認する流れを一体的に運用することで、さまざまな施策の効果測定や改善のスピードを高めています。
この取り組みにより、住民向けサービスの改善ポイントが具体的にわかるようになりました。また、職員の分析にかかる負担が軽くなり、検討の質が向上しています。事業評価の仕組みが定着したのも大きく、改善サイクルが回るようになったと話しています。
住民側にとってもメリットが大きく、生活実態の「見える化」により、子育て世帯・高齢世帯など“支援が必要な層”へ施策が届きやすくなります。【出典】八女市「オープンデータ」
URL:https://www.city.yame.fukuoka.jp/soshiki/12/dx/dxs/1583995463409.html
EBPM導入時の課題と対応策
EBPMの導入は、現場・情報政策とDX・企画財政が同じ方向を向くことが成功への近道です。以下、EBPM導入を成功させる3つのポイントをまとめました。
① 現場職員を巻き込む仕組みづくり
「上から押し付けられた」という気持ちを避けるため、現場が抱えている課題から逆算して分析テーマを決めましょう。職員が日頃困っていることを解決するためのダッシュボードを一緒に作り、小さな成功体験を積み重ねていくのがポイントです。
② 段階的な導入でハードルを下げる
いきなり高度な統計分析や大規模なシステム導入を目指すのではなく、今あるデータを整理してグラフにすることから始めてください。政策評価のための書式をテンプレート化して誰でも使えるようにし、対象分野を少しずつ広げていくアプローチが有効です。
③ 外部リソースの効果的活用
大学やシンクタンク、民間の専門家と連携して、評価方法の設計や因果関係の分析についてアドバイスを受けます。他の自治体との情報交換も、実際に使える知識を得るうえで有効です。
自治体のEBPM導入に関するよくある質問
最後に、自治体のEBPM導入に関するよくある質問と回答をまとめました。
Q1. EBPM導入にはどの程度の予算が必要ですか?
導入範囲や目的によって費用は大きく異なります。たとえば、外部講師を招いた研修であれば、数十万円で実施できることがあります。一方で、本格的なBIツールの導入や外部コンサルティングの活用を含めると、数百万円規模の予算が必要でしょう。
主な費用としては、BIツールの導入・運用費、職員研修費、外部専門家への支援費用が挙げられます。大切なのは、かけた費用に対してどれだけの成果が得られたかを必ず確認することです。
Q2. 小規模自治体でも効果はありますか?
十分に効果があります。むしろ、限られた予算と人員で運営している小規模自治体こそ、データに基づいてどこに力を入れるべきかを決めることが重要です。
クラウド型のツールを使ったり、近隣の自治体と一緒に研修を行ったりすることで、費用を抑えながら運用できるでしょう。
Q3. データ分析の専門知識がなくても導入できますか?
Excelが使えるレベルから段階的にスキルを身につけていきます。まずは操作が簡単なBIツールでデータの「見える化」に慣れ、必要に応じて外部研修や実際の業務に即した研修で理解を深めていけば問題ありません。なお、神戸市のように実践的な研修制度を整えると、職員への定着が早まる傾向があります。
まとめ
EBPMの基本は、毎日の業務に追われている状況を、少しずつ「改善できている証拠」を積み上げる時間に変えることです。いきなり大きな変化を求めるのではなく、日々の業務の中で「なぜこの結果になったのか」「どうすればもっと良くなるのか」を数字で確認する習慣を作ることから始めましょう。そして、その気づきを職員全体で共有すれば、組織全体のレベルアップにつながるはずです。
小さな改善を重ねるほど、暮らしの質は底上げされます。EBPMは、その土台になる考え方といえるでしょう。


4-150x150.png)
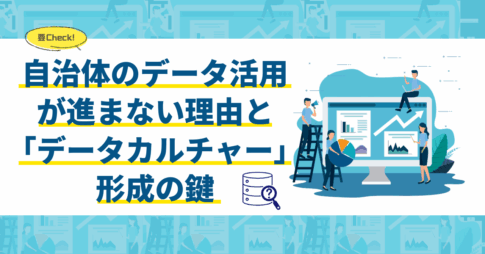
4-485x273.png)