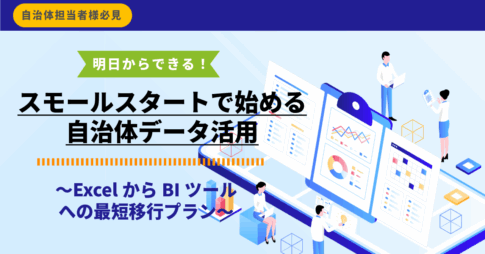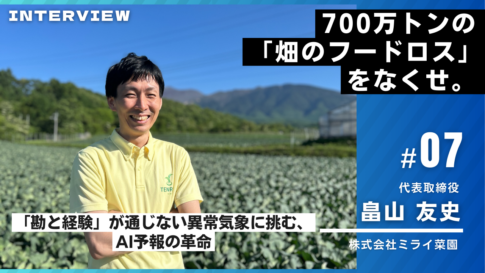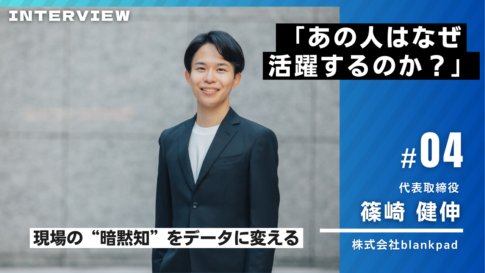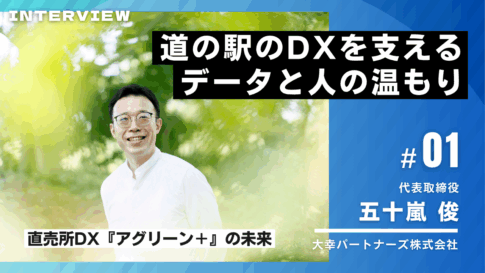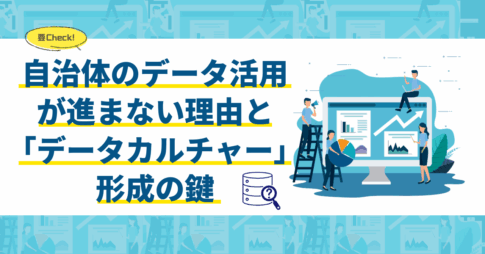全国の自治体において行政手続きのデジタル化やデータ連携が進む一方で、「ツールは導入したが、活用されていない」──そんな悩みを抱えるケースも少なくありません。
実は、この問題の本質はスキル不足ではありません。背景にあるのは”文化”の欠如です。デジタルマーケティングの世界で当たり前の「データドリブン」──さまざまなデータに基づく判断や行動が、行政組織では定着していないのです。ツールや制度をいくら整えても、データを活用する土壌がなければ、組織は変わりません。
いま求められているのは、「マインドセット改革」──すなわち「データカルチャー」の醸成です。
この記事では、「データカルチャー」とは何か、なぜ日本の自治体に根付きにくいのか、そしてどのように育てるのかを、成功事例と最新技術トレンドの両面から探ります。
データカルチャーとは何か?
「データカルチャー」とは、意思決定や業務改善において、データを基盤に考える文化的風土を指します。これは単なるデータ分析スキルや専門知識の有無ではありません。組織全体の「考え方」や「行動様式」そのものです。
欧米では、合理的根拠(エビデンス)に基づく政策立案「EBPM(Evidence-Based Policy Making)」が広く定着しています。政策の企画段階から、効果測定・評価に至るまで、一貫してデータに基づく判断が行われているのです。民間企業においても、マーケティングや経営戦略の現場では、データドリブンな意思決定が当たり前になっています。
一方、日本の自治体はどうでしょうか。近年、EBPMの推進やスマートシティ構想を通じて、データ活用への取り組みは確実に進みつつあります。しかし、データを日常的に参照し、政策判断に活かす”文化”として根付いているかといえば、まだ道半ばと言わざるを得ません。
いま行政に求められているのは、DXケイパビリティ──すなわち、組織・人材・イノベーション創出機能といった、DXを推進するために欠かせない能力の獲得・強化です。その土台となるのが、まさに「データカルチャー」なのです。
参考:Tableau「データカルチャーがデータと AI の活用の成功を推進」/NTTデータ経営研究所「地域DX」/「EBPM証拠に基づく政策立案」
なぜ日本の自治体にデータカルチャーは根付きにくいのか
なぜ、日本の自治体では、データカルチャ〜が根付きにくいのでしょうか。その要因となる3つの「壁」について解説します。
壁① 組織の縦割りとデータ共有不足
自治体は、管轄ごとにピラミッド化された縦割りの組織構造を持っています。その結果、データは部署ごとに分断され、他部署との共有が進みません。各部署が独自に業務を最適化しても、組織全体としては部分の最適化に留まってしまうのです。
横断的な政策の見直しや改善が行われにくい環境が、データ活用の大きな障壁となっています。
壁② スキル格差と人事異動による知識リセット
自治体職員の中で、データ分析を得意とする人材は非常に限られています。職員間のスキル格差は大きく、データ分析を実践する機会や経験も不足しがちです。
さらに深刻なのが、頻繁な人事異動による「知識のリセット」です。せっかく身につけたデータ活用のノウハウが次の担当者に引き継がれず、取り組みへの熱意も低下してしまいます。結果として、組織としての能力が蓄積されないという悪循環に陥っているのです。
壁③ 「前例主義」など心理的抵抗
多くの自治体では、「これまでこのやり方で進めていた」という安易な前例踏襲が続く保守的な組織風土が根強く残っています。
解決すべき課題があっても、「エビデンスが揃っていない」「前例がない」という理由で、新たな政策へのチャレンジを避ける傾向があるのです。この心理的な抵抗感が、データに基づく意思決定の定着を妨げています。
参考:日経BP「横串さしてよ縦割り行政 – PPPまちづくりかるた」/EBPMガイドブック
データカルチャーを支える最新技術トレンド
技術の進化は、データカルチャー醸成の”追い風”になっています。ここでは、自治体の現場を変える3つの技術トレンドについて解説します。
トレンド① AI・RPAによる業務の自動化と効率化
AI-OCR(紙の書類や手書き文字をAIでデジタルデータ化する技術)とRPA(定型的なパソコン作業を自動実行するソフトウェア)の組み合わせにより、紙帳票の内容を自動でシステムに入力できるようになりました。
札幌市では就学援助業務でAI-OCRを活用し、業務時間を70%削減(8,446時間→2,611時間)という成果を上げています。
また、AIチャットボットによる住民からの問い合わせ対応も広がっています。埼玉県戸田市では24時間365日対応を実現。その経済効果は年間約540万円と試算されています。
トレンド② 自治体間のシステム共同化・標準化
複数自治体による共同利用型システムの導入が進んでいます。鳥取県では県内全市町村による統合型校務支援システムで最大12.5億円の削減、富山県では9市町村による自治体クラウドとRPA共同利用を実現しました。
特に注目すべきは熊本県の事例です。県内全45市町村で子育てAIチャットボットを共同利用し、相談対応の大幅な低コスト化を達成。各市町村が個別に相談員を雇用すると年間約1億800万円かかるところを、県単独で開発・運営することで年間500万円に削減しました。
業務プロセスの標準化やデータフォーマットの統一により、自治体間のデータ連携も容易になりつつあります。
トレンド③ データ利活用を支える基盤整備
国によるエビデンスポータルの整備が進んでいます。エビデンスポータルとは、既存のエビデンスを整理し、概要や質を一覧できる形で公表するプラットフォームです。政策立案に必要なデータを効率的に収集できます。
代表例が、内閣府が提供する「経済・財政と暮らしの指標『見える化』データベース」です。47都道府県別・1,741市区町村別のデータを時系列で比較でき、1975年からのデータを利用可能。自治体間の地域差を「見える化」できます。
また、RESAS(地域経済分析システム)の活用事例も増えています。内閣府・経済産業省が提供するこのシステムは、地域経済に関するビッグデータを可視化します。愛知県知立市ではRESASで30歳代の転出超過を分析し、住宅政策を総合戦略に反映。滋賀県高島市では地域経済循環分析により、観光戦略を強化しました。
データを「見る」「触る」体験ができる環境が整うことで、職員のデータリテラシー向上が後押しされているのです。
参考:地方公共団体における行政改革の取組(令和2年3月27日公表)
成功する自治体の共通点
データカルチャーの醸成に成功しつつある自治体には、どのような特徴があるのでしょうか。3つの先進事例を見ていきましょう。
つくば市(茨城県)
つくば市では、市長主導で「スーパーサイエンスシティ構想」を掲げ、最先端技術を活用し都市機能の効率化・最適化を目指すスマートシティ実証を積極的に推進しています。
注目すべきは、職員研修を通じた庁内でのデータ活用意識の醸成です。令和4~6年度の主査級研修後アンケートでは、9割以上の職員が「データ活用を進めたい」と回答しました。
研修と実証を繰り返す中で、デジタル技術を”目的ではなく課題解決の道具”として捉える意識が、組織全体に根付き始めています。
参考:つくばスーパーサイエンスシティ構想/自治体DX推進参考事例集【第3.0版】
北九州市(福岡県)
北九州市は、全庁一体でDXを推進するため、市長を本部長とする「デジタル市役所推進本部」を令和2年に設置しました。推進本部のもとで、必要に応じてテーマごとのワーキンググループ(WG)を立ち上げ、部局横断で課題解決に取り組んでいます。
この取り組みの特徴は、デジタル化を単なる業務効率化ではなく、全庁の協働を促す仕組みづくりの一環と位置づけている点です。縦割り組織の壁を超えるための、戦略的なアプローチといえるでしょう。
参考:北九州市のDX推進体制①
神戸市(兵庫県)
神戸市では、スタートアップとの協働プログラム「Urban Innovation KOBE」を通じて、行政課題を”見える化”し、職員と外部パートナーがチームで解決策を検証しています。現場職員が自ら課題を定義し、外部の視点を取り入れることで、課題解決に向けた意識改革や新たな発想が生まれているのです。
具体例として、各社個別に導入されているバスロケーションシステムの統合的な整備などが挙げられます。神戸市の取り組みは、新技術やスタートアップの知見を”導入すること”自体ではなく、”行政文化を変える触媒”として活用している点が特徴的です。
参考:Urban Innovation Kobeを活用した取り組み/神戸市 – Urban Innovation JAPAN
共通点
これら3つの自治体には、明確な共通点があります。
第一に、トップの明確なリーダーシップと全庁的な支援体制です。市長自らがDXやデータ活用の重要性を発信し、組織全体で取り組む姿勢を示しています。
第二に、職員主体の試行と小さな成功体験の積み重ねです。現場職員が実際にデータを触り、小さな成果を実感することで、データ活用への抵抗感が薄れていきます。
第三に、成果や学びを共有し、横展開する仕組みです。一部署の成功を全庁で共有することで、組織全体の底上げにつながります。
そして最も重要なのが、技術を「目的」ではなく「文化を育てる道具」として扱う姿勢です。ツール導入そのものをゴールとせず、組織文化の変革こそが真の目的だと認識しているのです。
データカルチャーを根付かせる3ステップ
では、具体的にどのようにデータカルチャーを育てればよいのでしょうか。実践的な3つのステップをご紹介します。
Step1:教育・研修でデータ活用への抵抗感を解消する
データカルチャーの定着は、職員一人ひとりが「なぜデータを使うのか」を理解するところから始まります。まずは手元にあるデータを使った小さな実践から着手し、データが業務改善につながる感覚を掴むことが重要です。
専門知識を詰め込むよりも、”自分ごと化”された体験を通じて理解を深めることが、データ活用への心理的ハードルを下げます。近年では生成AIやノーコード分析ツールを活用した研修も有効です。
Step2:仕組み化でツール・基盤を整備
次に必要なのは、誰もがデータにアクセスできる仕組みです。自治体では、庁内データを横断的に扱うために、データを集計・可視化するBIツールや、複数部署の情報を統合するデータ連携基盤の整備が進められています。
こうしたデータ基盤の整備は、単なる技術導入ではありません。法務・セキュリティ部門を含めた全庁的な取り組みが求められます。「スモールスタート」「データ民主化」を意識すれば、属人的な活用から組織的活用へスムーズに移行できます。
Step3:評価と改善のサイクルを定着
データカルチャーの成熟には、継続的な評価と改善の仕組みづくりが欠かせません。成功事例や失敗からの学びを共有し、組織全体で振り返る仕組みを設けることが、文化の定着を後押しします。
小規模なABテストや効果検証の繰り返しが、学びのサイクルを生み出します。目標を達成するための重要な業績評価の指標であるKPI(重要業績評価指標)設定と進捗可視化の習慣化も必要です。日常的にデータを見ながら継続的に改善を行い、“データを見る文化”から”データで判断する文化”へと移行していくのです。
参考:自治体 DX 全体手順書 【第 4.0 版】/UX note「ステップ方式で分かる データ活用で成長企業に変わる方法」/XIMIX「データ活用文化を組織に根付かせるには? DX推進担当者が知るべき考え方と実践ステップ」
まとめ ― データカルチャーが描く行政の未来
データカルチャーの醸成は、ツールや制度の整備だけでは実現しません。職員一人ひとりの意識変化と、組織としての学びのサイクルがあって初めて、文化として根付いていくのです。
そのためにも、教育・研修によってデータ活用への抵抗感を解消し、全庁的な仕組みづくりで環境を整える必要があります。そして継続的な評価と改善によって、“データを見る文化”から”データで判断する文化”へと進化させていくことが重要です。
本記事で紹介した成功事例に共通するのは、技術を「目的」ではなく「手段」として捉え、組織文化の変革に向き合っている点です。トップのリーダーシップと現場の小さな成功体験を積み重ねながら、着実に前進しています。
データカルチャーが成熟した先にあるのは、データを軸に職員・市民・民間がつながり、より柔軟で持続可能な行政を形づくる未来です。エビデンスに基づく政策立案が当たり前になり、限られた資源を最適に配分可能になります。これにより、住民一人ひとりのニーズに応える行政サービスが実現するのです。

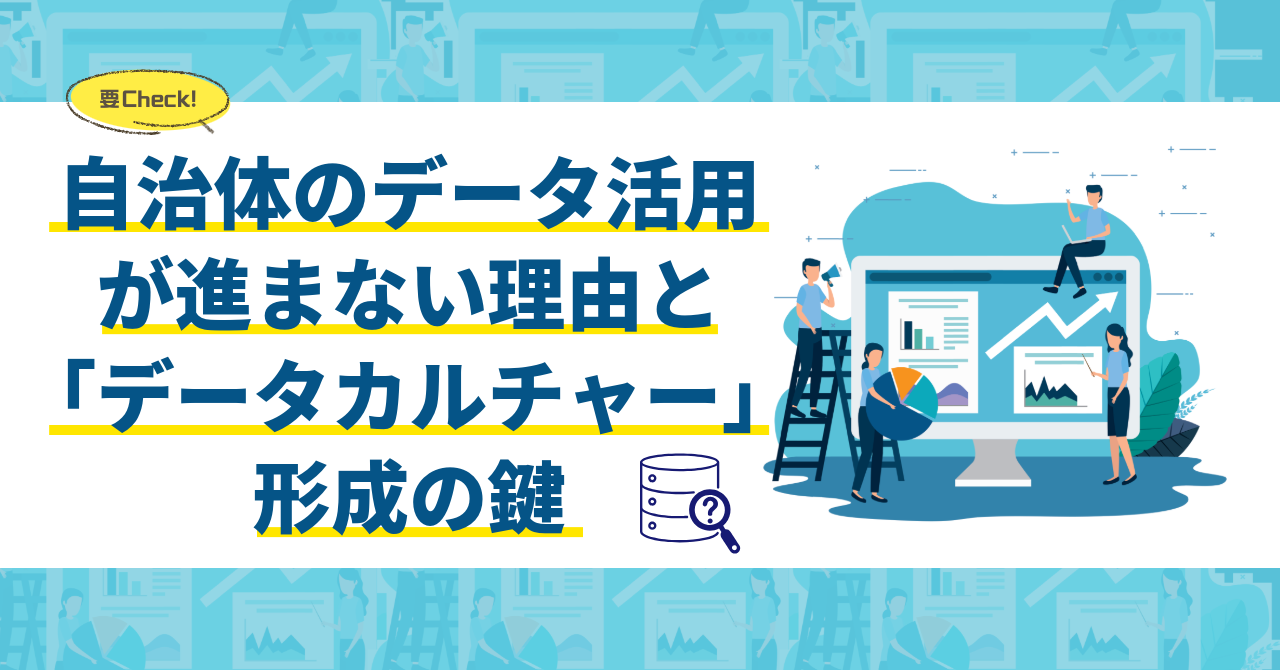
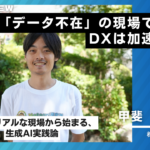
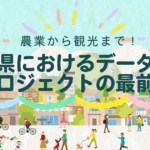
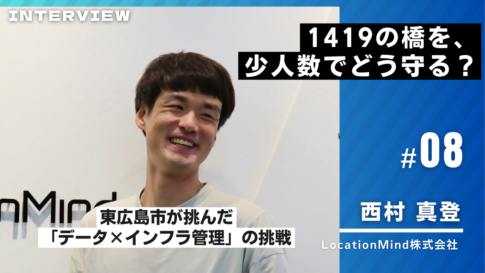

4-485x273.png)