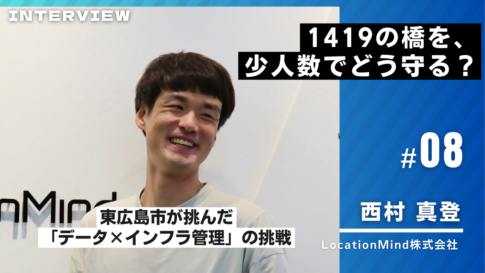〜未来をつくる「楽しい」地方創生の秘密に迫ります〜
政府が「地方創生」の取り組みを本格的に始めてから、2024年でちょうど10年という節目を迎えました。そして今、これまでの成果と課題を踏まえ、次の10年を見据えた「地方創生2.0」という新しいステージへと進もうとしています。
今回は、この「地方創生2.0」をデータとデジタル技術で力強く推進している地域、大分県の取り組みに焦点を当ててご紹介していきます。大分県がどのように「稼ぐ力」を磨き、「ひと」が輝く「楽しい地方」をつくろうとしているのか、その秘密を探っていきましょう!
はじめに:データが加速させる「地方創生2.0」の時代
地方創生10年の成果と残された課題
この10年間、地方創生の取り組みを通じて、日本各地で地域を良くしていこうという関係者の皆さんの意識や行動は高まりました。地方公共団体は、国からの財政支援(交付金)や人材支援、情報支援(RESASなど)を積極的に活用し、自律的で主体的な取り組みを進めてきたのです。その結果、地方移住への関心は高まり、実際に移住する人の数も増加傾向にあります。
しかしながら、国全体で見ると、日本の人口は2008年をピークに減少しており、特に東京圏への一極集中という大きな流れを変えるまでには至っていません。
特に深刻なのが、若者や女性が地方を離れてしまう「社会減」です。
「地方創生2.0」では、人口減少が続いても経済成長し、社会を機能させるための適応策を講じること、そして「若者や女性にも選ばれる地方(=楽しい地方)」をつくることを主眼としています。その鍵となるのが、デジタル技術の徹底活用と、データに基づいた客観的な戦略立案、つまり「データ駆動型(データドリブン)」の地域経営なのです。
大分県の挑戦:データ駆動型(データドリブン)の地域経営へ
大分県は、この新しい時代の地方創生をリードするべく、データ活用に積極的に取り組んでいます。
大分県が2022年3月に策定した「大分県DX推進戦略」では、デジタル技術ありきで施策を考えるのではなく、社会背景や外部環境の変化に際し、デザイン思考を用いてユーザー(県民や来訪者)の声をしっかり聞き、「将来どうありたいのか」というビジョンを描くことを重視しているそうです。
これは、今まで観光や地域活性化の施策が「勘と経験と度胸」に頼りがちだったのに対し、客観的なデータに基づいて課題を発見し、解決策を提案していく、データドリブンな地域経営へと舵を切ったことを意味しています。
「稼ぐ力」を磨く!大分県の産業DX戦略
観光DX:ビッグデータ分析で観光客の行動を変える
観光は、地方の「稼ぐ力」を左右する重要な産業です。大分県では、特に観光客の行動をビッグデータで分析し、より効果的なプロモーションや施策の展開に役立てています。
大分県内のDMO(観光地域づくり法人)である「ツーリズムおおいた」は、民間企業と連携してキャッシュレスデータを分析しています。この分析の結果、大分県を訪れる観光客の中でも、20代の若年層と60~70代のシニア層の来訪と消費が特に活発であるという顕著な傾向が見つかりました。
また、大分県北部地域(中津市、豊後高田市、宇佐市)では、観光客の「地域内滞在時間」を延ばすために、携帯電話の位置情報ビッグデータを活用した実証実験が行われました。
この実験では、観光客が多く立ち寄る飲食店の席にQRコードを設置し、読み込んだ観光客に「お薦めの次の観光地」を表示するという試みを実施しました。このデータ分析を通じて、観光客が実際にどのスポットを同日中に併用しているのかを客観的に把握し、その結果に基づいて、マイカー利用を前提とした新しい観光モデルコースが作成されたのです。これらの新しいコースには、地域の主要な観光地だけでなく、「おんせん県おおいた」らしく温泉で締めるプランや、お土産購入が期待できる道の駅などを盛り込む工夫がされています。
データドリブンなアプローチは、観光プロモーションの成果を消費金額という最適な指標で可視化し、施策のPDCA(計画・実行・評価・改善)サイクルをスピード感を持って回すために不可欠な要素となっています。
参考:令和5年度大分県観光実態調査報告書/大分県が挑むデータ起点の観光マーケティング 来訪者の消費額増を狙った「ミッドナイトおおいた」とは?/令和3年度ビッグデータ活用による旅客流動分析実証実験事業
スマート農林水産業:経験と勘をデータで進化
農業や漁業といった一次産業においても、DX(デジタルトランスフォーメーション)は進んでいます。大分県では、「経験と勘」に頼りがちだった分野にデジタル技術を導入し、生産性の向上を目指しています。
スマート農業:水稲へのドローンによる農薬散布や、GPSを活用した直進アシスト機能付きトラクターの普及が進められています。また、白ねぎなどの品目では、民間企業と連携して生育を管理するためのシステム開発や、空撮画像を用いた画像分析による生育診断も行われ、導入が進められています。
スマート漁業:養殖業を支援する取り組みが注目されます。例えば、赤潮の被害を軽減するため、2019年度までに佐伯湾など特定の海域に観測機器が導入され、そのデータがインターネットで配信されています。
こうしたデジタル技術の導入は、深刻化する担い手不足や生産性の向上といった課題を乗り越え、地域の基幹産業を未来へとつなぐために重要な挑戦だと言えるでしょう。
参考:大分県スマート農林水産業推進方針/高性能衛星データを活用したスマート農業サービスの開発事業/和牛繁殖農家をICTでサポート
「ひと」が輝く持続可能な地域社会の実現(大分日田市の例)
若者・女性に選ばれる「楽しい地方」へ
若者や女性が地方を離れる要因の一つに、職場の魅力不足や、地域に残る「アンコンシャス・バイアス」(無意識の思い込み)や「ジェンダーギャップ」(男女格差)が挙げられます。
この課題に対し、大分県日田市(ひたし)の取り組みは参考になります。日田市の市長は、若い女性に選ばれるまちとは、女性に限らず多様性が尊重され、誰もが自分らしく生きることができるまちだと考えているそうです。
そのため、日田市では、性別を問わない「ひた魅力発信隊」の募集や、災害対策に女性の視点を取り入れる「女性防災士会」の設立などを行っています。
行政、企業、地域が一体となって、男女の固定観念をなくし、働き方や職場環境の改革を進めること、そして若者や女性にとって「心地よさ、楽しさ」がある地域をつくることが、地方創生2.0の重要な要素なのですね。
デジタル技術による生活基盤の維持
人口減少や高齢化が進む地方では、医療・福祉、交通、買物など、日常生活に不可欠なサービスを維持することが困難になりつつあります。大分県では、この生活基盤の維持にもデジタル技術を積極的に活用しています。
行政サービスの効率化:行政手続きの100%電子化を目標とし、県民の利便性を向上
子育て・介護分野:保育所や認定こども園で登降園管理システムを導入し、朝夕の混雑解消や欠席連絡の負担軽減
地域の安全確保:不法投棄対策にAIカメラを導入し、人や車を判別した上で、異常を検知するとリアルタイムで通知を行う
このように、大分県ではデジタル技術を駆使して、住民の利便性を高め、行政や地域の担い手の負担を減らし、持続可能な生活基盤を構築する努力が続けられているのです。
参考:大分発 営農の見える化を実現 農業再生の道開く原価管理/大分県DX事例集(令和4年度版)/進む『観光DX』その事例と展望
4. まとめ:データと「共創」が未来を拓く
大分モデルから学ぶ成功の法則
大分県が観光、農業、そして生活サービスといった多岐にわたる分野でDXを進めている事例は、地方創生が従来の「勘と経験」から、「データと客観性」に基づく戦略へと移行しつつあることをはっきりと示しています。
データ活用は、限られたリソースの中で最も効果的な施策を見つけ出すための羅針盤となり、地域資源に高い付加価値を生み出すことを可能にするのです。
そして、大分モデルの成功の鍵は、行政内部の努力だけでなく、外部との「共創」にあります。観光DXにおけるDMOと民間企業のデータ連携、ものづくり中小企業へのDXパートナーとの伴走型支援、そして先端技術を持つ大学や専門家からの知見の活用など、多様な関係者が一体となって地域課題の解決に取り組むエコシステムが構築されているのですね。
未来の担い手である皆さんへ
地方が直面する人口減少や東京圏への一極集中といった問題の是正は、私たち日本全体が戦略的に挑戦すべき課題です。しかし、地方創生2.0の考え方が示すように、デジタル技術を最大限に活用し、地域独自の文化や資源、そして「ひと」の力を組み合わせる「新結合」(イノベーション)によって、地方は再び希望と幸せを実感できる持続可能な地域へと進化できるはずです。 皆さんの住む町や、これから関わるかもしれない地方が、データと情熱によって、さらに魅力的で「楽しい」場所になることを期待しています!


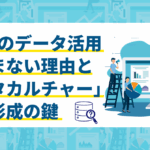
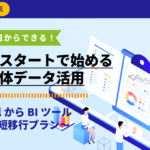
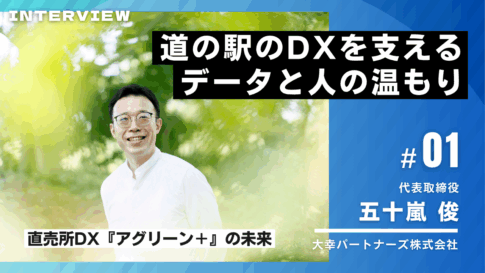

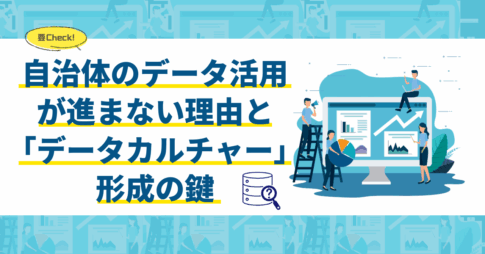

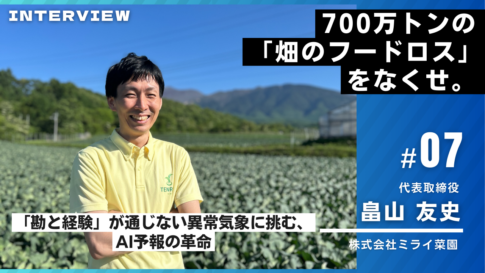
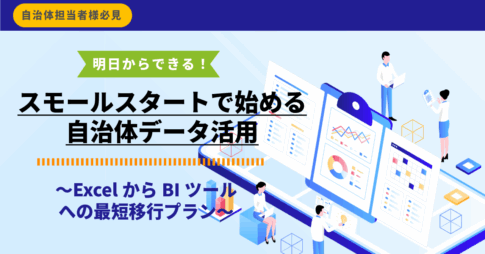
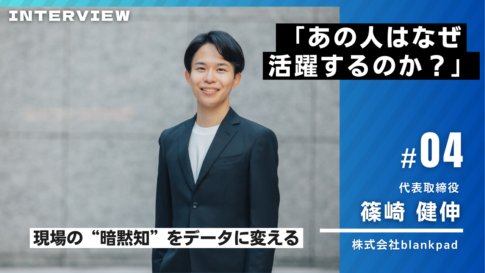

4-485x273.png)