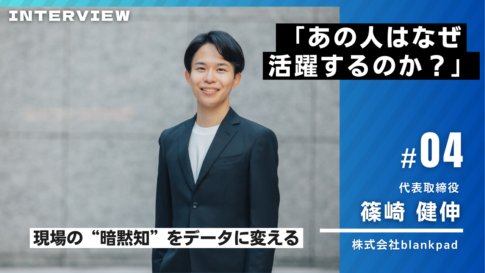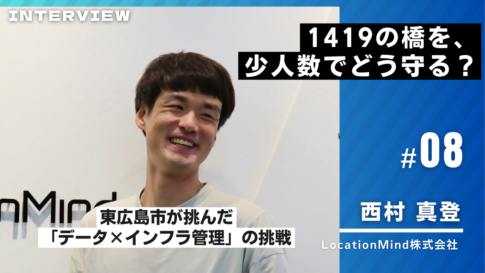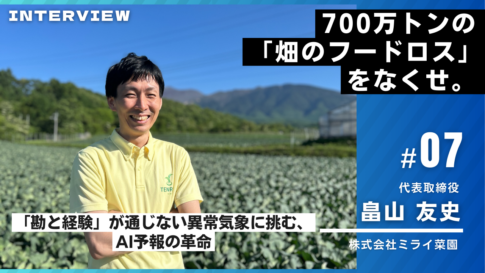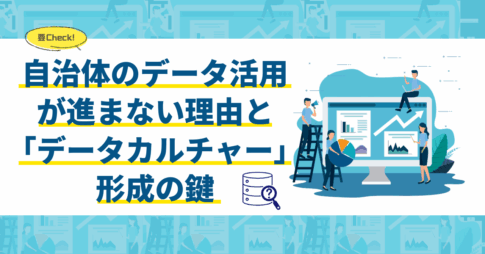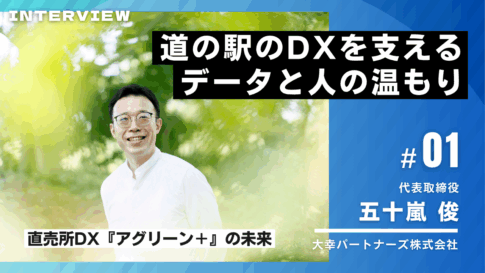自治体におけるデータ活用の重要性が高まる中、限界になるのがExcelによる集計や分析です。
この記事では、BIツールを活用したスモールスタートの方法を紹介し、Excelの延長で実践できる移行ステップを具体的に解説します。
関市の成功事例も紹介し、自治体職員がすぐにデータ活用を始めるための実践的な手順をご紹介します。
BIツールとは?Excelと何が違うのか
BIツールは自治体のデータ活用を加速させる基盤です。ここでは、BIツールの役割とExcelとの違いを通じて、導入の必要性を明らかにします。
BIツールの基本機能と役割
BIツール(Business Intelligenceツール)は、組織内に分散しているデータをまとめて管理し、分析や可視化を行うことで、意思決定を支援するソフトウェアです。
複数の部署のデータを自動的に集め、グラフやダッシュボードでわかりやすく表示できるため、現場職員から管理職まで、誰もが同じ情報を共有できます。これにより「感覚」ではなく「数値」に基づいた政策判断が可能となります。
従来の表計算ソフトを使った場合は、集計作業に多くの時間がかかっていました。しかし、BIツールを活用すれば自動で集計でき、より迅速に意思決定を行えるようになります。
Excelでは難しい「見える化」の限界と課題
長い間、自治体ではExcelを使ってデータを集計する方法が一般的でした。しかし、データが担当者ごとに管理されやすく、更新や情報の共有のたびに手間を要してきました。さらに、Excelには扱えるデータの量や処理速度に限界があるため、部署間で連携するのも難しいという問題があります。
BIツールを導入することで、クラウド上でリアルタイムの更新や可視化が可能となり、地図やグラフによる表示も容易になります。これにより、特定の担当者に依存しない、組織全体で共有テータに基づいた判断ができるようになるのです。
自治体で進むBIツールの活用シーン
自治体ではデータの分散や共有の難しさが課題です。そのためBIツールの活用によって、業務効率の向上や政策判断の質の改善が図られています。ここでは、具体的な活用事例を解説します。
データ分析による政策立案(EBPM)
国が推進する「EBPM(Evidence Based Policy Making)」は、政策形成に欠かせない考え方です。BIツールを導入すれば、財政データや人口統計、公共施設の稼働率などを一元的に分析できます。
防災では避難所利用実績を可視化して配置の最適化を検討でき、観光や子育て支援ではアンケート結果を定量的に把握するなど、多面的な活用が可能です。根拠のあるデータ分析が、より的確な政策判断を支える基盤となります。
市民サービスや業務改善への応用
BIツールは政策立案だけでなく、業務改善にも効果を発揮します。窓口対応件数や問い合わせ内容を可視化すれば、混雑時間帯や課題の傾向を把握でき、職員配置の最適化が可能です。
また、アンケート集計を自動化することで、市民の声を即時に反映したサービス改善が実現します。この結果、報告作業の効率化とリアルタイムな情報共有が促進され、自治体全体の業務改善が推進されます。
事例紹介:岐阜県関市の「関市データダッシュボード」
自治体の中でも先進的にBIツールを導入した関市の事例を通じて、スモールスタートの具体像と効果を見ていきます。
導入の背景と目的
岐阜県関市では、庁内のデータが部署ごとに分散し、分析や共有に時間がかかっていました。そこで、2023年度から「関市データダッシュボード」の整備を開始。Excelで管理していた統計データをBIツールに集約し、可視化と分析を自動化しました。
目的は、政策立案のスピードと透明性を高め、職員がデータに基づいて説明できる環境を整えることです。これにより、現場でも「データを活用する文化」が根付きはじめています。
導入効果と今後の展開
BIツール導入後、関市では庁内からの分析依頼件数が約3倍に増加しました。各部署が自発的にデータを活用し、会議資料の作成時間も大幅に短縮されました。
また、職員のデータを読み解く力(データリテラシー)も向上しています。今後はオープンデータなど、外部のさまざまなデータと連携することも検討されています。
スモールスタートではじめたこの取り組みが、今では庁内全体でデータを活用する動きに広がっていることが、大きな成果です。
参考:関市データダッシュボード|関市役所公式ホームページ/自治体業務におけるデータ利活用(Tableau Japan 提供資料)
ExcelからBIツールに移行するメリットとデメリット
ここでは、Excelによる業務からBIツールへ移行することで、得られるメリットや注意点についてわかりやすくまとめます。導入を検討する際の参考としてご活用ください。
移行のメリット:自動化・共有・リアルタイム化
BIツール導入の最大の利点は、データの自動化と可視化による意思決定の迅速化です。定期的な集計を自動化することで、担当者の負担を減らし、人為的ミスを防げます。
さらに、クラウド型のツールであれば複数の部署がリアルタイムに同じダッシュボードを共有でき、情報伝達が効率的になります。Excelでは難しかった複雑なグラフや比較も簡単に作成でき、透明性の高い業務報告が可能です。
デメリット:費用・学習コスト・データ整備
導入初期には費用や教育面の課題もあります。ライセンス料やサーバー整備費に加え、職員の操作教育やデータ整備にも時間が必要です。とくに、データの重複や形式の不統一があると移行が滞ることもあります。
リスクを抑えるには、無料トライアルや限定部署での検証からはじめ、段階的に展開するスモールスタート方式が有効です。
参考:自治体業務におけるデータ利活用(Tableau Japan 提供資料)/地方公共団体におけるデータ利活用の推進に関する研究報告書
導入の流れとスモールスタートの進め方
初期導入では全庁展開よりも小規模な実践から始めることが成功の鍵です。段階的な導入プロセスとその要点を解説します。
Excelデータを活かした小規模導入ステップ
BIツール導入を成功させるには、まずExcelで管理している既存データを活用して小規模に始めるのが現実的です。
初期段階では、問い合わせ件数の分析などテーマを絞り、低コストのツールで可視化を試しましょう。得られた成果を庁内で共有し、効果を実感することがさらなる拡大への動機付けとなります。小さな成功体験が、組織変革への第一歩となります。
自治体が避けるべき失敗と成功のコツ
導入を成功させるには、「目的」を明確にすることが最も重要です。「何を見える化したいのか」「どの業務を改善したいのか」を具体化し、関係部署を巻き込んで進めることで、形だけの導入を防げます。成功している自治体の事例を参考にし、段階的な展開とフィードバックの積み重ねで全庁的な活用を実現しましょう。
まとめ:明日からできる小さな一歩
ここまで紹介した事例や手順を踏まえ、明日から実践できる具体的なアクションを整理します。
今日からできるアクションリスト
まずは、Excelで管理している主要データを整理し、どの情報を可視化することで、業務改善につながるかを検討しましょう。そのうえで、無料のBIツールを使って、簡単なダッシュボードを試作します。
これにより、職員がデータの価値を実感でき、次のステップへの意欲が高まります。最初の一歩は実際に試行することです。
データ活用文化の第一歩を踏み出す
自治体でのデータ活用は、単に新しいシステムを導入するだけでなく、職員が日常的にデータを活用して判断する文化を育てることも大切です。BIツールを活用すれば、こうした習慣が自治体に根付きやすくなります。 関市のような成功事例に学び、スモールスタートから始めることが成果を生む鍵です。今こそ、自治体全体でデータ活用の文化を育み、持続可能な行政運営を実現しましょう。

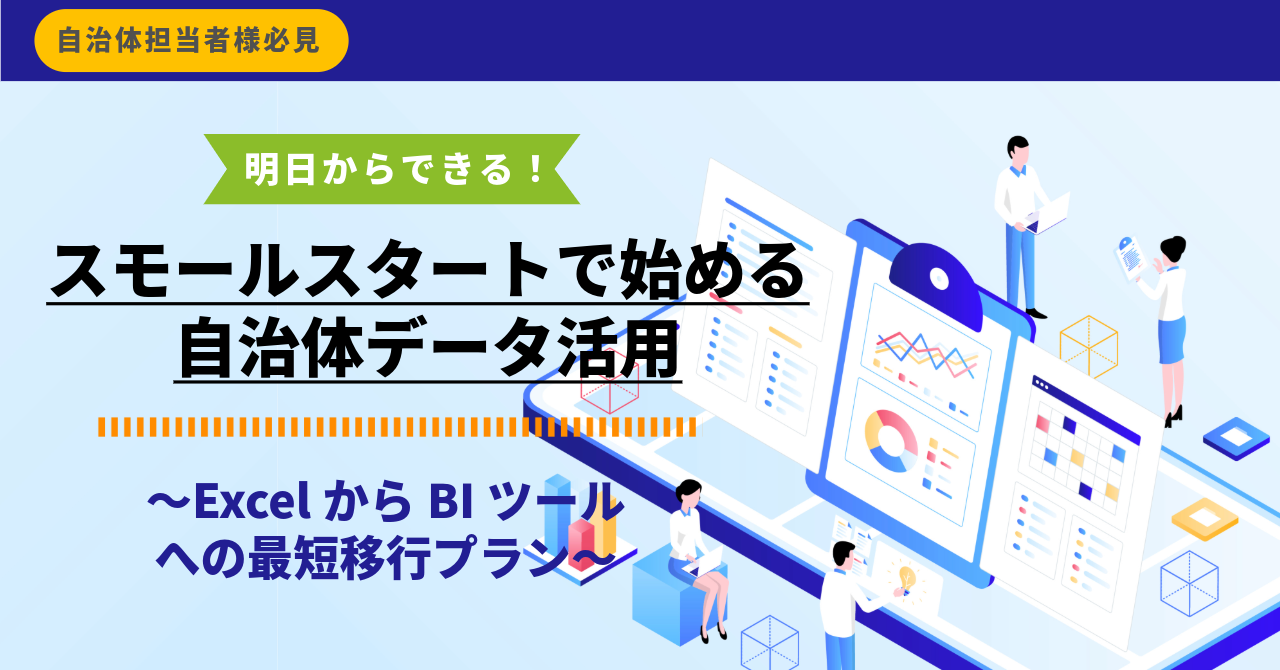
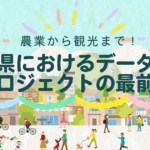
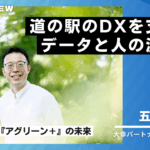
4-485x273.png)